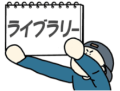昨年夏から「米がない」「価格が約2倍」など米騒動が続いている。その前年(令和5)は高温障害と水不足で1等米比率がコシヒカリでも通常80%から5%まで堕ちるなど異常な品質低下があり、生産農家や農協、それに卸業者それぞれが出荷調整もしくは備蓄に走って一気に流通量が減っていった。この異変に農林省の動きは鈍く、ようやく備蓄米の放出を決めたがことごとくがゴテゴテ。そもそもが・・・ ①誰が作った米かはわからない
①誰が作った米かはわからない
②品種や産地ごとに混ぜられてしまう
③流通経路が長く複雑で鮮度が落ちコストは高くなる
④移動と保管を繰り返すため品質低下しやすい
⑤輸送回数が多く傷みやすい
その上に、今回のように流通過程で買いだめ売り惜しみのような投機的商行為が行われたら、まさに「令和の米騒動」になるのは目に見えている。生産調整も含めて別本的な見直しが必要なのだ。
2月 18
2025
2025